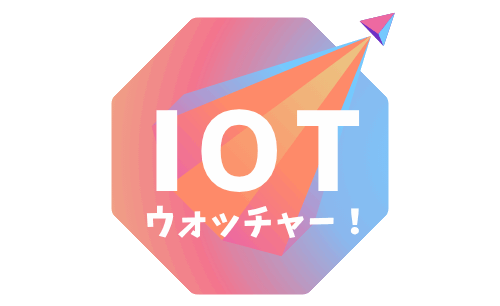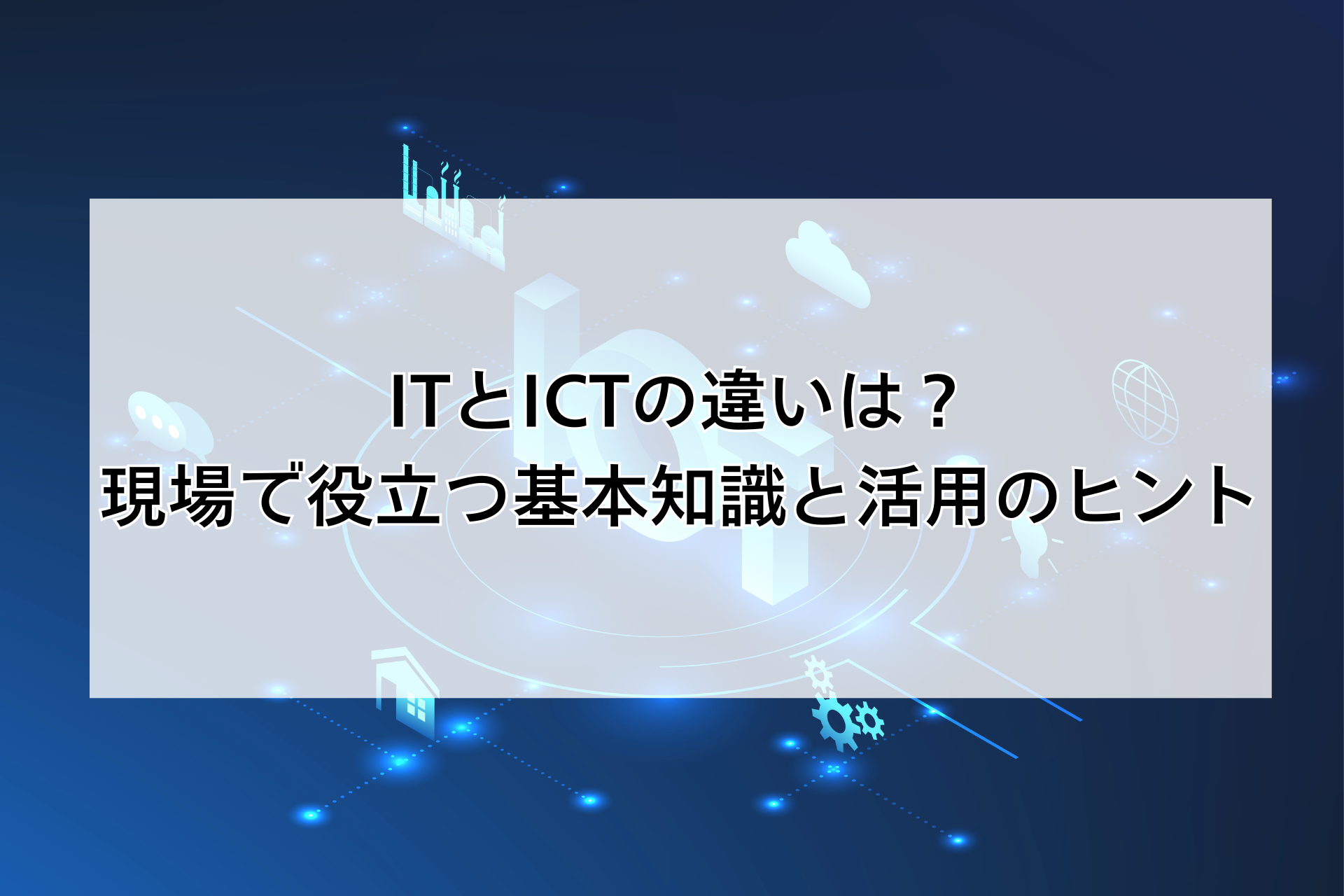現場の業務効率化やデジタル化を進める中で、ITとICTという言葉をよく目にするようになりました。しかし、実際にはこの2つの違いがあいまいなまま使われているケースも少なくありません。ITもICTもどちらも技術を指す用語ですが、意味や活用の範囲には明確な違いがあります。
特にIoTやDXといった取り組みを推進するうえでは、それぞれの用語の本質を正しく理解することが、組織の共通認識を築き、効果的な活用につながります。本記事では、ITとICTの定義や違いを整理しながら、なぜ今ICTが注目されているのか、IoTとの関係性を含めてわかりやすく解説します。現場での実践に役立つ視点をぜひお確かめください。
ITとICTの意味
業務のデジタル化や設備管理の効率化を進めるうえで、ITやICTという用語を耳にする機会は増えています。どちらも技術を活用する概念ですが、言葉の意味や適用範囲には違いがあります。まずは、それぞれが指す内容を整理し、現場やビジネスでの理解を深めましょう。
ITとは
ITとは、Information Technology(情報技術)の略で、コンピュータやネットワークを用いて情報を処理・管理・活用するための技術全般を指します。ビジネスにおけるITの主な目的は、業務の効率化や自動化、情報資産の最適な活用にあります。
たとえば、会計ソフトや勤怠管理システム、製造ラインの制御装置などもITの一部です。これらは人間が手作業で行っていた業務をシステム化・自動化し、正確性とスピードを高めることに貢献しています。また、データベースの構築・運用やクラウドの利用なども、IT活用の代表例です。
ITの特徴は、主に情報の処理や管理に焦点がある点にあります。情報をどう収集し、どう整理し、どう活用するかという一連の技術を支えるのがITの役割です。通信そのものよりも、情報を効率的に取り扱うための技術基盤として位置づけられています。
近年ではAIやビッグデータといった新たな分野もITに含まれ、企業活動の中心的な存在となっています。ITは業種を問わず、すべてのビジネスや社会インフラの土台を支える不可欠な技術といえるでしょう。
ICTとは
ICTとは、Information and Communication Technology(情報通信技術)の略で、ITに通信(Communication)の概念を加えた言葉です。インターネットやモバイルネットワークを通じて、情報を人やシステムの間でやりとりし、共有・活用する技術全般を指します。
ITが情報の処理や管理に重点を置いているのに対し、ICTはその情報をどう伝えるか・誰とつなぐかという点までを含んでいます。たとえば、ビデオ会議やチャットツール、遠隔医療システム、教育のオンライン配信などは、ICTの典型的な活用例です。
企業では、営業活動のオンライン化や社内コミュニケーションの円滑化、テレワーク環境の整備など、業務の効率化と同時に情報のつながり方そのものを変える取り組みが進んでいます。また、教育現場や公共サービスにおいても、ICTは人と人をつなぎ、情報格差の解消に貢献しています。
ICTは単なる技術の集合ではなく、情報を通じた新たな価値の創出や社会の仕組みの変革をもたらす力を持っています。そのため、近年ではIT以上に幅広い分野で注目され、活用の場が広がりつつあります。
それぞれが使われてきた背景を知る
ITとICTは似たような文脈で使われることも多い言葉ですが、発展してきた背景には違いがあります。ITという言葉は1970年代から1980年代にかけて、主に欧米を中心に使われ始め、コンピュータを活用して情報を処理・管理する技術として確立されていきました。企業活動のデジタル化や事務作業の自動化といった、内部業務の効率化が主な関心事だった時代です。
一方、ICTという概念が広く使われ始めたのは1990年代以降。インターネットの普及により、情報は一人で処理するものから共有・連携するものへと変化し、通信の役割がより重要視されるようになりました。とくに教育や医療、公共インフラといった社会全体に関わる分野で情報をどう伝え、どうつなぐかという視点が求められ、ICTという言葉が登場したのです。
日本では行政や教育現場を中心にICTという言葉が浸透し始め、今では自治体のDX推進計画や学校のGIGAスクール構想など、多くの施策に活用されています。ITが効率化の文脈で語られることが多いのに対し、ICTはつながりや社会全体の最適化といった広い視点で使われる傾向があるのです。両者の違いを知ることで、技術導入の目的や役割をより明確に捉えることができます。
ITとICTの違い
ITもICTも情報を扱う技術を表す言葉ですが、その意味や使われ方には違いがあります。業界や場面によって混同されやすい両者ですが、正しく理解すれば導入や活用の方向性を明確にする助けになります。ここでは、言葉としての範囲や使われ方の違いに注目しながら整理していきます。
言葉の範囲と使われ方
ITとICTは、どちらも情報技術を意味する用語ですが、それぞれが示す範囲には明確な違いがあります。IT(Information Technology)は、主に「情報を処理・保存・管理する」ことに重きを置いた技術の総称で、業務システムの導入やデータベースの構築、AIやクラウドの活用などが代表的なIT活用の領域です。
一方のICT(Information and Communication Technology)は、ITの範囲を含みつつ、ビデオ会議やチャットツール、オンライン授業、テレメディスン(遠隔医療)といった人と人・人とモノをつなぐ仕組みが含まれるのが特徴です。
使われ方の違いにも傾向があります。企業のシステム部門やIT業界では、日常的にITという言葉が用いられますが、行政や教育分野ではICTが主に使われることが多くなっています。これは、単なる情報処理ではなく、社会の情報インフラとしての技術活用に重点が置かれているためです。
つまり、ITは情報処理の基盤技術、ICTはその基盤を使って情報をつなぎ、広く活用するための仕組みを含む言葉と捉えると、両者の違いがより明確になります。用途や導入目的に応じて、言葉を適切に使い分ける視点が大切です。
現場で混同されやすい場面
ITとICTは意味の違いこそあるものの、現場ではしばしば混同されて使われています。その背景には、どちらも情報技術を活用するという共通点があるため、使い分けが曖昧になりやすい事情があります。
たとえば、製造業でのデジタル化を進める際に、IT導入による業務効率化とICT活用による遠隔支援や通信環境の整備が同時に語られる場面があります。このようなケースでは、IT=業務改善、ICT=通信基盤といった役割の違いを意識しないと、導入目的が不明確になり、現場での混乱を招く可能性があります。
また、教育や医療の現場では、IT活用・ICT教育など似た表現が混在することも少なくありません。ITはコンピュータ機器やソフトウェアの導入そのものを指すことが多いのに対し、ICTはそれを活用して“誰とどのように情報を共有するか”までを含めた概念です。
混同されることで、技術導入の優先順位や評価軸が曖昧になり、せっかくの施策が効果を発揮しにくくなることもあります。現場ではIT=情報の処理、ICT=情報の共有とつながりといった基本を意識し、導入や運用方針を明確にすることが重要です。
IoTやDXとの関係
ITやICTという言葉は、近年よく耳にするIoT(モノのインターネット)やDX(デジタルトランスフォーメーション)とも密接に関係しています。これらの言葉は似ているようでいて、それぞれ異なる役割と意味を持っています。
まず、IoTとはセンサーや機器をインターネットにつなげ、リアルタイムに情報を収集・共有する技術のことです。IoTを成立させるには、機器側での情報取得(IT)と、その情報を外部とつなぐ通信機能(ICT)の両方が欠かせません。つまり、IoTはITとICTの融合の上に成り立っているといえます。IoTの仕組みやセンサーの種類については「IoTセンサーの仕組みは?主な種類と導入の流れを解説」で詳しく紹介しています。
一方、DXは企業や組織がデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを抜本的に変革する取り組みを指します。DXの推進には、ITによるシステム基盤の整備と、ICTを通じた関係者間の円滑な連携が重要な鍵となります。
現場でITとICTの使い分けを意識することで、IoTはどの部分を補うのか・DXには何が不足しているのかといった視点が持てるようになります。それぞれの技術の関係性を理解することが、導入の成功や課題解決につながる第一歩となるのです。
ICTが注目される理由
インターネットやクラウドサービスの発展とともに、ICTの役割はますます重要になっています。単に情報を処理するだけでなく、情報をどう共有し、どう活かすかが問われる現代において、ICTは業務やサービスの質を左右する基盤技術として注目されています。ここでは、社会や企業におけるニーズの変化を踏まえて、その背景を見ていきましょう。
社会や企業でICTが求められる背景
ICTが注目されるようになった背景には、社会全体で進む情報化と、それにともなう働き方や生活の変化があります。たとえば、少子高齢化が進む中で、限られた人材で効率的に業務を回す必要性が高まっています。その際、場所や時間に縛られずに業務を進められるICTの導入は、柔軟な働き方や省力化を実現する手段として不可欠です。
企業においても、グローバル化や競争激化に対応するためには、迅速かつ的確な情報共有が求められます。ICTを活用することで、複数拠点をまたぐプロジェクトでも、リアルタイムにデータを共有し、スムーズに意思決定が行えるようになります。リモート会議やクラウド業務ツールの利用は、もはや特別なものではなく、業務の基本インフラとして広く浸透しています。
また、感染症の拡大によりテレワークや非対面対応のニーズが急速に拡大したことで、ICTの重要性は一層顕在化しました。オンラインでの顧客対応、遠隔での設備監視、在宅勤務に必要な通信環境の整備など、あらゆる場面でICTの力が活かされています。
このように、ICTはもはや一部の専門分野に限られた技術ではなく、社会と企業の持続的な成長を支える重要なインフラへと進化しているのです。
国や自治体が推進するICT活用
ICTの活用は、民間企業だけでなく、国や自治体においても重点施策として進められています。たとえば、政府が推進する「デジタル田園都市国家構想」では、地方における医療・教育・交通などの課題をICTで解決し、地域の活性化を図る取り組みが展開されています。オンライン診療や遠隔授業、交通の最適化など、地域の暮らしに直結する領域でICTの導入が加速しています。
また、行政手続きの電子化もその一環です。住民票や納税証明書のオンライン申請、マイナポータルを通じた情報確認など、住民サービスの利便性向上と行政側の業務効率化の両立が図られています。災害時の情報共有や避難所の管理にもICTが活用され、リアルタイムでの状況把握と指示伝達が可能になりました。
教育分野では「GIGAスクール構想」により、小中学校へのタブレット端末配布やネットワーク環境の整備が進められ、児童生徒一人ひとりがICTを活用した学習に取り組める体制が構築されています。
こうした国や自治体の取り組みは、ICTの必要性と可能性を示すものであり、企業や個人にとっても導入の後押しとなる環境が整ってきたことを意味します。
業務にICTを取り入れるメリット
ICTを業務に取り入れることで得られるメリットは多岐にわたります。まず大きいのは情報共有の迅速化です。たとえば、クラウドサービスを活用すれば、社内外の関係者とリアルタイムでデータを共有でき、意思決定のスピードが飛躍的に向上します。
次に、業務の自動化と効率化が挙げられます。チャットボットによる問い合わせ対応、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による定型業務の自動処理など、繰り返しの作業をICTで代替することで、人手をより創造的な業務へと振り分けられます。
さらに、テレワークなど柔軟な働き方の実現も重要なポイントです。ICTを活用すれば、在宅勤務やサテライトオフィスでの作業が可能になり、ワークライフバランスの向上にも寄与します。
また、顧客対応の質の向上にもつながります。CRMシステムの活用で顧客情報を一元管理し、個別対応やマーケティング施策に活かすことで、より満足度の高いサービス提供が可能になります。
このようにICTの導入は、単なる作業効率の改善にとどまらず、企業全体の生産性向上や競争力強化に直結する施策として、今後ますます欠かせないものとなっていくでしょう。
ITやICTをIoTとどうつなげる?
現場のデジタル化を進める中で、IoT・ICT・ITは密接に関わりながら、それぞれ異なる役割を担っています。IoTはセンサーや機器からデータを集める技術、ICTはそのデータを活用して人とシステムをつなぐ技術です。では、実際にIoTとICTをどう連携させれば、現場の業務効率化や遠隔監視に役立つのでしょうか?その具体的な方法を解説します。
合わせてチェック!
IoT機器や通信環境を整え、データをリアルタイムに取得・共有できる体制をつくるには、ICTとの連携が欠かせません。実際に現場での遠隔監視をどう実現するかについては「IoT遠隔監視の基本と導入のポイント」をご参照ください。
IoT機器とICTの連携方法
IoT機器とICTを効果的に連携させるには、現場で収集したデータをどのように活かすかを明確に設計する必要があります。たとえば、温度センサーや人感センサーなどのIoT機器で取得したデータを、クラウドや社内ネットワークを介してICTシステムに送信することで、遠隔での監視や自動通知が可能になります。
このとき重要なのがネットワークとデータ活用基盤の整備です。IoT機器からのデータは、LPWAやWi-Fi、LTEなどの通信方式を使って送信されますが、通信の安定性やセキュリティを確保するためには、ICTの知識が不可欠です。また、データを蓄積・分析するためには、クラウドサービスやオンプレミスのサーバーに適切な環境を構築し、可視化ツールやアラート通知の仕組みを整える必要があります。
さらに、IoTのデータを業務に活かすには、ERPやSFA、設備保全管理システムなど既存のICTツールと連携させることも効果的です。たとえば、生産設備の稼働状況をリアルタイムに共有し、異常検知と同時に担当者へ通知を行うなど、現場の反応速度を高められます。
このように、IoTのデータを集める力と、ICTのデータを活かす力を組み合わせることで、業務全体を最適化し、DXを着実に前進させることができます。
センサーや通信の活用の仕方
IoTの中核を担うのがセンサーと通信技術です。センサーは温度・湿度・振動・CO₂濃度など、現場のあらゆる状態を数値として捉える役割を果たします。これらのデータをリアルタイムで活用するには、センサーから得た情報を確実に伝える通信インフラが不可欠です。
通信方式には、使用環境や目的に応じた選択が求められます。たとえば、近距離かつ低消費電力が求められる場面ではBLE(Bluetooth Low Energy)が、広域かつ省電力通信にはLPWA(Low Power Wide Area)が有効です。また、即時性が必要な監視にはWi-FiやLTEの利用が適しています。有線通信も安定性を重視する設備管理においては今なお有効な手段です。
さらに、複数のセンサーを1つのゲートウェイに集約し、クラウドへ送信する構成を取ることで、設置や管理の負担を軽減できます。データはクラウド上で蓄積・分析され、ダッシュボードでの可視化や異常時のアラート通知に活用されます。
こうしたセンサーと通信の連携は、単なるデータ収集にとどまらず、現場の意思決定や省力化を支える鍵です。設備の状態変化をリアルタイムに見える化することで、現場の管理精度と対応力を大きく向上させることができます。
遠隔監視や設備管理をICTで支える戦略
現場での設備稼働や環境の状態を、離れた場所からでも把握・管理できる体制を整えることは、多拠点展開を行う企業や省人化を進めたい組織にとって非常に重要です。ここで活躍するのが、IoTの遠隔監視とICTの情報共有・制御の仕組みです。
具体的には、現場のセンサーやカメラ、ゲートウェイ機器をICTインフラとつなぎ、クラウド上にデータを集約・可視化します。その情報を、関係者がいつでも・どこでも確認できるようにすることで、異常の早期発見や迅速な初動対応が可能になります。
また、遠隔監視は設備の異常兆候や環境変化を検知するだけでなく、設備の稼働状況を長期的にモニタリングすることで、計画的な保全(予防保全や予兆保全)へと活用することもできます。これは突発的なトラブルを未然に防ぎ、保守工数やダウンタイムの削減につながります。
さらに、ICTを使って社内外の関係者とリアルタイムにデータを共有すれば、専門部署や本社が現場の判断を支援することも可能になります。このような仕組みづくりは、現場の判断スピードと精度を高め、企業全体の運用効率を向上させる戦略的なICT活用と言えるでしょう。
まとめ
ITとICTは、どちらも情報や通信に関わる技術を示す言葉ですが、それぞれの意味や使われ方には違いがあります。ITは技術そのものを指し、ICTはその技術を活用して人や情報をつなぐ仕組みに焦点を当てています。特に近年では、IoTやDXとの連携においてICTの重要性が増し、現場の遠隔監視や業務の効率化に直結する存在として注目されています。
ICTを適切に理解し、自社の課題に応じて適切に取り入れることで、より柔軟で強固な情報基盤を構築することが可能になります。本記事が、ITとICTの違いを明確にし、今後のデジタル活用の指針となれば幸いです。