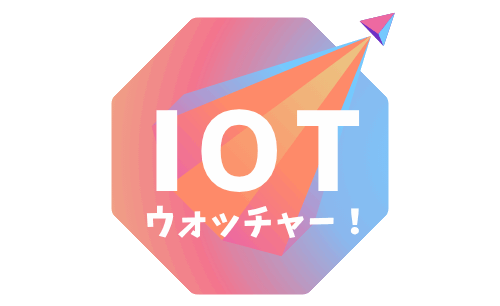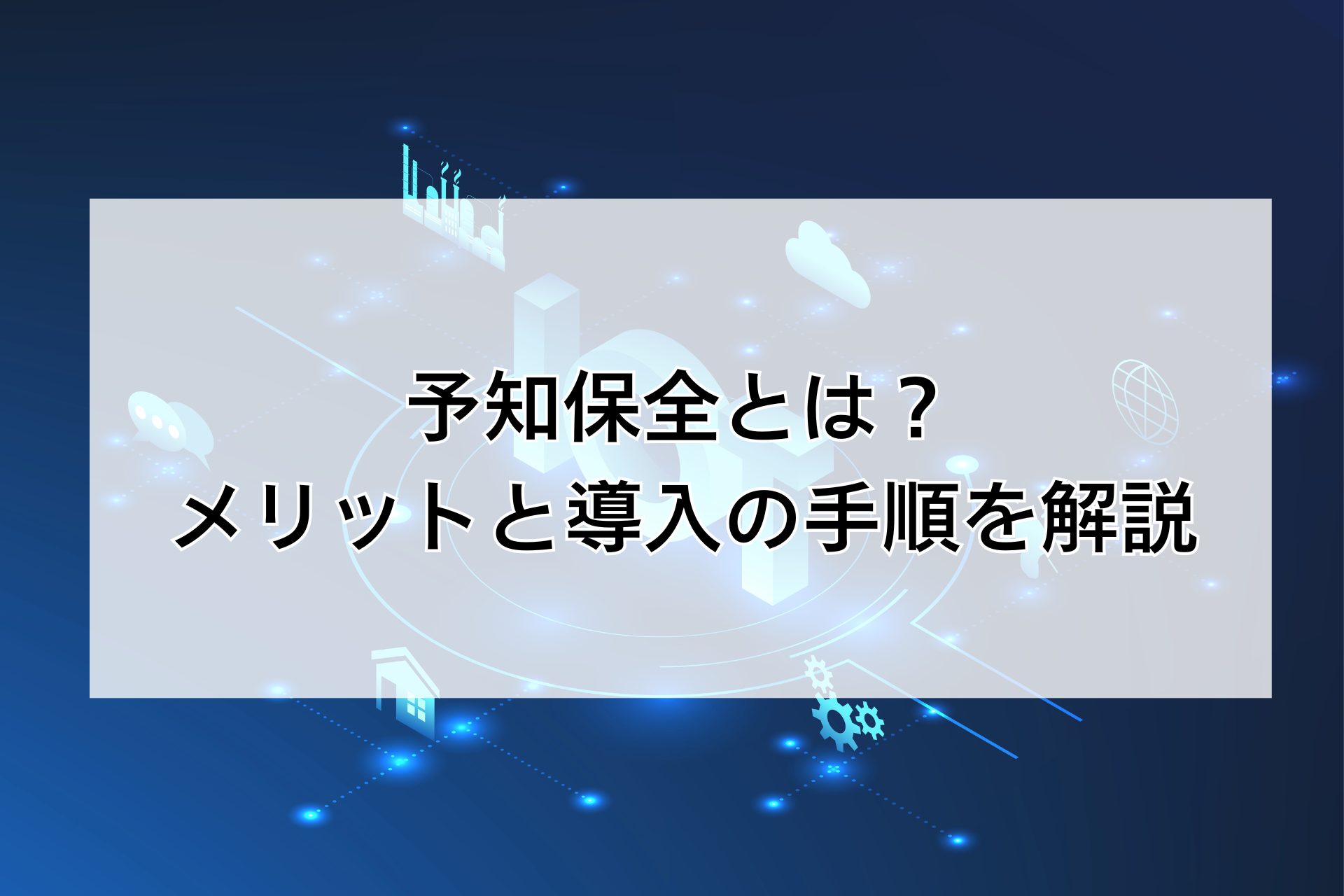突発的な設備トラブルによる生産停止や、熟練技術者の減少による保全力の低下に悩む現場は少なくありません。そんな課題に対し、近年注目されているのが予知保全です。
設備の状態をセンサーで常時モニタリングし、異常の兆候をデータから読み取ることで、故障を未然に防ぐことが可能になります。従来の事後保全や定期保全に比べて効率的かつ合理的な方法として、多くの企業が導入を検討している技術です。
本記事では、予知保全の基本や従来手法との違い、活用技術、進め方、導入時の注意点までをわかりやすく解説し、現場のDX推進を後押しします。
予知保全とは
予知保全とは、センサーやAIなどを活用して設備の状態を常時監視し、異常の兆候を早期に捉えて故障を未然に防ぐ保全手法です。従来の定期的な点検や、トラブル発生後の対応に比べ、より精度の高いタイミングでメンテナンスを行うことができます。設備の振動、温度、電流、圧力といったデータを収集し、通常時とのわずかな違いから劣化や故障の兆しを捉えることで、計画的な対応が可能です。
このアプローチは、製造業をはじめとした現場において、突発的な設備停止による生産ロスや、点検作業の無駄を減らす目的で注目されています。また、人手不足や技術継承の課題を抱える中でも、データに基づいた客観的な判断ができるため、現場力の底上げにもつながるでしょう。
予知保全は、設備管理DXの中でも注目されている取り組みのひとつです。より広い文脈での導入ポイントは「設備管理DXとは?現場を支える技術と導入のポイント」でご確認ください。
予知保全が登場した背景
予知保全が注目されるようになった背景には、設備トラブルの増加や保守現場の変化があります。従来は、ベテランの経験や感覚に頼った点検が一般的でしたが、少子高齢化に伴い、技術者の高齢化や人手不足が深刻化しています。こうした中で、現場の判断をデータで支える仕組みが求められるようになりました。
また、製品ライフサイクルの短縮や納期の短縮化が進み、設備の稼働率向上とダウンタイム削減が重要視されています。加えて、スマートファクトリー化やDXの潮流により、現場のあらゆる情報を可視化し、最適化する動きが加速。その一環として、予知保全は生産ラインの安定稼働を維持しながら、保守業務の効率化と計画性を高める手段として登場しました。全体像を知るには「スマートファクトリーの基本を解説!メリットと導入の進め方」も参考になります。
予防保全や事後保全との違い
予知保全は、従来の予防保全や事後保全とは異なるアプローチを取ります。事後保全とは、設備が故障してから修理を行う手法で、コストは低く抑えられる反面、突発的な生産停止や損害のリスクが大きくなります。
一方、予防保全は、故障が起きる前に定期点検や部品交換を行うことで、トラブルを未然に防ぐ手法です。ただし、劣化していない部品も含めて交換することがあり、ムダなコストが発生しやすいという課題があります。
それに対し予知保全は、設備の状態をリアルタイムで監視し、データに基づいてそろそろ異常が発生しそうだと判断した時点で対処する方法です。必要なときにだけメンテナンスを行うため、保守コストを最適化しつつ、突発故障のリスクも低減できます。また、データを活用することで、技術者の経験や勘に頼らない運用が可能になり、現場の属人化対策にもつながります。
予知保全を導入するメリット
予知保全を導入することで、現場全体のリスクを減らし、経営の安定化にも貢献する手法として注目されています。ここでは、具体的なメリットを3つご紹介します。
突発故障を減らして安定稼働につなげる
予知保全を導入する最大の利点の一つは、突発的な設備の故障を未然に防げる点です。これまでの保全では、設備が停止してから修理に取りかかる事後対応が多く、突然のトラブルによって生産ライン全体がストップするリスクが常にありました。予知保全では、センサーによって収集されたデータからわずかな異常の兆候を捉え、必要なタイミングで対策を講じることができます。
たとえば、モーターの振動が通常と異なる動きを示したり、軸受け部分の温度が徐々に上昇しているといった兆候を、AIや解析ソフトが検知。こうした情報に基づいてメンテナンスの時期を判断することで、設備が止まる前に適切な処置が可能になります。これにより、生産の計画が大きく乱れることなく、安定した稼働を維持しやすくなります。
ダウンタイムが減ることで納期遅延や損失リスクも抑えられ、顧客からの信頼維持にもつながります。予知保全は、安定操業を支える基盤として、現場にとって大きな安心材料となるのです。
人手やコストのムダを減らせる
予知保全を取り入れることで、人手や保全コストのムダを大幅に削減できます。これまでの保全は、定期的に点検を実施したり、一定期間ごとに部品を交換する予防保全が主流でした。しかしこの方法では、まだ使える部品を早期に交換してしまったり、異常がない箇所も点検対象になるなど、労力とコストが過剰になりがちです。
一方、予知保全は設備の状態をリアルタイムで監視し、異常の兆候が見られたときにのみ必要な対応を取ります。これにより、作業員が無駄な点検や交換を行う必要がなくなり、保守作業の効率が向上します。点検や修理のタイミングが明確になるため、必要な人員を最小限で配置できるのもメリットです。
また、トラブルの発生による緊急対応や突発修理は、費用が割高になりやすい傾向があります。予知保全を行えば、こうした急な出費も防げるため、設備管理にかかるトータルコストを安定的に抑えることが可能です。人的資源とコストを賢く使い、現場全体の生産性を底上げする仕組みとして効果を発揮します。
設備を長持ちさせて資産を守る
予知保全は、設備の寿命を延ばし、企業の資産を守るうえでも有効なアプローチです。機械や装置は、本来の性能を維持して運用されている限り、長く使い続けることができます。しかし、気づかないうちに小さな不具合が蓄積し、それが大きなトラブルへ発展すると、設備全体の劣化を早めてしまうこともあります。
予知保全では、センサーや解析技術を使って、稼働中の設備の温度や振動、圧力などを常時モニタリングします。わずかな変化でも異常の兆候として捉え、早期に点検や部品交換を行うことで、重大な故障を未然に防ぎます。このサイクルを繰り返すことで、設備は安定した状態で使い続けることができ、結果として全体の延命につながります。
設備を長く使えるということは、新規購入や大規模な修繕の頻度を抑えられるということでもあります。企業にとっては投資の回収期間を延ばさずに済み、資産管理の面でも大きなメリットとなります。予知保全は、単なる故障防止にとどまらず、設備の健全な運用と資産保全を両立する戦略といえるでしょう。
予知保全に使われる主な技術
予知保全は、目視や経験だけでは実現できません。現場の状態をデータで見える化し、リアルタイムに分析・判断するための技術が不可欠です。そのためには複数の技術が連携して初めて機能します。ここでは、予知保全の実現を支える代表的な技術について紹介します。
合わせてチェック!
設備の状態をリアルタイムで把握するには、各種IoTセンサーの特徴と仕組みを理解しておくことが大切です。詳しくは「IoTセンサーの仕組みと導入の流れ」もあわせてご覧ください。
センサーで設備の状態を見える化する
予知保全の出発点は、センサーを使って設備の状態を見える化することにあります。目に見えない温度の上昇やわずかな振動、音の変化、電流の異常なども、センサーを用いれば数値として正確に把握できます。これにより、普段は見逃されがちな異常の兆候を捉えやすくなります。
使用されるセンサーには、温度センサーや振動センサー、電流センサー、超音波センサー、圧力センサーなどさまざまな種類があります。対象となる設備や監視目的に応じて、最適なセンサーを選定することが重要です。たとえば、設備の劣化や異常を温湿度の変化から察知するケースも増えています。詳しくは「IoT温湿度センサーの仕組みと効果」をご確認ください。
また、複数のセンサーを組み合わせて設置することで、より立体的かつ精度の高い監視が可能になります。たとえばモーターなら、振動と温度を同時に測定し、両方のデータから状態を判断する手法がよく用いられます。
センサーの選び方や取り付け位置は、効果的な予知保全を行ううえで非常に重要です。適切に設計・導入すれば、これまで感覚に頼っていた保全作業を、より客観的で精緻なものへと変えることができます。
通信とクラウドでデータを集めるしくみ
センサーで収集したデータは、設備に取り付けられたままでは活用できません。リアルタイムで監視・分析を行うには、データを集約し、遠隔からアクセスできる環境が必要です。そこで活躍するのが、通信ネットワークとクラウド技術です。
工場や施設内では、センサーからデータを送信するためにLPWA(省電力広域通信)、Wi-Fi、5G、Ethernetなどの通信手段が用いられます。通信方法の選定は、設置環境や送信頻度、データ量などによって変わります。
集められたデータはクラウドに蓄積され、管理画面やアプリを通じて関係者がいつでも確認できます。これにより、複数拠点に分かれた設備も一元的に管理でき、異常の早期発見と迅速な対応が可能になります。
また、クラウド上でデータを分析したり、過去の履歴と照合したりすることで、より精度の高い予兆判断が実現します。通信とクラウドは、センサーデータを使える情報に変えるうえで欠かせない基盤となります。
AIや統計で異常を予測する方法
予知保全では、収集したデータをどう活用するかが最大のポイントとなります。ここで活用されるのが、AIや統計的手法による異常予測です。センサーから得られた大量のデータをもとに、設備の挙動パターンを学習し、通常と異なる動きが見られた際に、異常の兆候として自動的に検知する仕組みです。
具体的には、機械学習アルゴリズムを使って異常値を検出したり、回帰分析によって将来的な劣化傾向を予測したりします。深層学習を用いて、過去の異常パターンを学習し、類似ケースを早期に発見する活用例もあります。
AIによる予測の魅力は、人間の目や経験では気づきにくい兆候を拾えることにあります。たとえば、わずかな振動の変化や短時間の温度上昇なども、パターンとして捉え、事前にアラートを出すことが可能になります。
ただし、精度を上げるには十分なデータ量と継続的なチューニングが必要です。導入時はまず単純な統計的分析から始め、徐々にAIモデルへと段階的に高度化させるアプローチが現実的です。
画面で可視化し、すぐに対応できる仕組み
どれだけ高度な予測ができても、それを現場で活かせなければ意味がありません。予知保全では、取得したデータやAIの解析結果をわかりやすく表示する仕組みも非常に重要です。多くのシステムでは、ダッシュボード形式の管理画面を通じて、設備の状態や異常兆候を視覚的に確認できるようになっています。
たとえば、設備ごとの温度や振動のグラフをリアルタイムで表示し、しきい値を超えた場合には色やアラートで即座に通知されます。また、過去データと現在の状態を比較しながら、劣化傾向をひと目で把握できるレポート機能も一般的です。
可視化によって、現場担当者がデータを見てすぐに対応判断できるため、トラブルの初期対応が迅速になります。複数拠点を遠隔で監視する際も、一覧画面で全体の状態を一括確認でき、管理負荷を大きく下げる効果があります。
また、WebブラウザやタブレットからアクセスできるUI設計にすることで、場所を選ばず状況を把握できる点も利点です。現場ですぐに気づけて、すぐ動ける体制をつくるには、データの見せ方も含めた設計が欠かせません。
予知保全の進め方と必要な準備
予知保全の導入には、明確な目的と段階的な取り組みが欠かせません。いきなりすべての設備に適用するのではなく、小規模な設備から始めて、効果を見ながら徐々に拡大するのが現実的です。ここでは、実際の導入ステップを整理し、準備すべきポイントや現場でつまずきやすい部分を押さえておきましょう。
まずは対象設備を決める
まずは、どの設備に導入するかを明確にすることから始めましょう。すべての設備に一斉導入するのは現実的ではないため、故障リスクが高いものや、停止すると生産に大きな影響を及ぼす設備を優先的に選定します。
選定基準としては、過去のトラブル履歴や保全コスト、稼働率、部品の劣化傾向などのデータが参考になります。また、比較的センサーデータが取得しやすい設備や、制御系との連携がシンプルな機器から始めることで、技術的なハードルを下げることができます。
導入初期に無理のある機器を選ぶと、データがうまく取れなかったり、異常判定が曖昧になったりすることもあります。逆に、状態変化がわかりやすい設備を選ぶことで、PoC(試験導入)やその後の社内展開をスムーズに進められます。
まずは設備の重要度やトラブル頻度を分析し、「この設備で成果が出せれば他にも応用できそうだ」という視点で候補を絞り込むことが大切です。
試験導入(PoC)で効果を確かめる
対象設備が決まったら、いきなり本格導入せず、まずはPoC(Proof of Concept)と呼ばれる試験導入を行います。これは「実際に効果があるのか」「運用上の課題はないか」を見極めるための検証プロセスです。
PoCでは、センサーの取り付けやデータ収集、分析ツールとの連携を小規模に実施します。この段階で、データの質や量、しきい値の設定、アラートの出し方などを確認し、現場の業務にどのように組み込めるかを検討します。
たとえば「どの程度の振動が異常とみなせるか」「温度上昇に対するアラートの頻度は適切か」など、実際の運用に即した条件を細かく調整していきます。
また、現場のスタッフが扱いやすいUIになっているか、アラートを受けて迅速に行動できる体制があるかも重要な確認ポイントです。PoCによって得られた知見は、正式導入の設計に直結します。
失敗してもいいから試す、というよりも、確実に成功に近づくための実証としてPoCを丁寧に設計・実行することが成功のポイントです。
うまくいけば全体に広げていく
PoCで一定の成果や手応えが得られたら、対象設備や拠点を段階的に広げていきます。いきなり全社展開するのではなく、類似の設備や運用条件が近い現場から展開を始めると、ノウハウの再利用がしやすく、導入効率も高まります。
このフェーズで重要なのは再現性です。PoCで得た成功パターンを、他の現場や設備にも展開できるよう、仕組みとして整えていきます。たとえば、センサーの設置位置や分析アルゴリズム、しきい値の設定などをテンプレート化しておくと、現場ごとの調整工数を減らせます。
規模を広げると、データ量の増加やネットワーク負荷、アラートの過多といった新たな課題が見えてくることもあります。このため、拡大フェーズにおいても継続的に効果を検証しながら、システム構成や通知運用の見直しを進めることが求められます。
全体展開の目的は現場ごとの個別対処ではなく、全社レベルの最適化です。その視点を持ちながら、着実に広げていくことが、設備管理の高度化と持続的な効果につながります。
運用ルールを決めて継続的に活用する
予知保全は一度導入して終わりではなく、データを活かし続けるための運用ルールづくりが欠かせません。たとえば、異常傾向を検知した際の対応フローや、アラートの優先順位、メンテナンス判断の基準などを、事前に明確にしておく必要があります。
また、どの頻度でデータをレビューするか、どの部門が分析・判断を担うかといった運用体制も整備しておきましょう。対応の属人化を避けるためには、点検・保全作業の記録と連携し、データベースとして蓄積する仕組みも有効です。
継続運用では「誰が、いつ、何を判断するのか」があいまいになると、せっかくのシステムも形骸化してしまいます。特に人事異動や担当者変更が起きても安定して運用できるよう、マニュアルやナレッジの共有も欠かせません。
さらに、設備や業務内容が変化すれば、分析モデルやセンサー構成の見直しも必要になります。定期的なレビューを行い、運用ルールもアップデートしていくことで、予知保全の効果を持続的に高めていくことができます。
予知保全を導入するときの注意点
予知保全は、設備トラブルの未然防止や保守業務の効率化に大きく貢献しますが、導入すればすぐに成果が出るわけではありません。現場ごとの設備環境や運用体制に応じた工夫が求められます。とくに初期段階では、センサーやシステムの選定・設置の仕方、既存機器との整合性、現場担当者の理解と協力など、いくつかの壁に直面する可能性があります。ここでは、導入時に注意すべき主なポイントを整理します。
正確なデータを集める工夫が必要
予知保全の成否を左右するのは、取得するデータの質です。どれだけ高度な分析ツールやAIを使っても、センサーから取得する情報がノイズを含んでいたり、測定箇所が適切でなかったりすると、異常を正確に検知できません。
たとえば、温度や振動を監視する際には、設備の構造や動作モードに応じて最適なセンサーの種類・設置位置・固定方法を選定する必要があります。誤差の大きいセンサーを使ってしまったり、外部環境の影響を受けやすい場所に設置してしまうと、誤検知や見落としにつながります。
また、定期的にキャリブレーションを実施することで、センサーの経年劣化やドリフトによるズレも抑えられます。さらに、データの時系列性や連続性を保つためには、通信途絶や記録ミスを防ぐネットワークやログ管理の整備も重要です。
正確なデータ収集は、予測の前提であり、異常検知の精度に直結します。設備や現場の特性を把握しながら、信頼できるデータ基盤を構築することが大切です。
古い設備との相性を考える
既存の設備、とくに長年使われてきた旧型の機器に対して予知保全を導入する場合、いくつかの技術的な制約が生じることがあります。たとえば、通信ポートが備わっていない機器や、デジタル信号に対応していない制御装置などでは、センサーやゲートウェイの設置に工夫が必要です。
また、機械の構造が密閉されていて内部にアクセスしづらい場合、計測ポイントの選定が困難になることもあります。こうしたケースでは、振動や電流といった間接的な指標から異常を推定する方法を検討する必要があります。
導入にあたっては、設備の年式やメーカー、回路構成を把握したうえで、「どこに・どのようなセンサーを使えば効果的か」を個別に判断することが大切です。場合によっては、部分的な改造や、中継装置の追加といった対応も求められます。
さらに、古い設備は故障履歴や仕様書が不明確な場合もあるため、導入前に可能な限り現場ヒアリングを行い、潜在的な課題を洗い出しておくことが有効です。設備の世代を問わず、現場全体の最適化を目指す視点が必要です。
担当者のスキルや運用体制も大事
技術面の整備だけでなく、人と運用体制にも目を向ける必要があります。いくらシステムを導入しても、それを扱う担当者が使いこなせなければ、活用は定着しません。特に中小規模の現場では、保全担当者のITリテラシーや分析スキルにばらつきがあるため、適切な教育や研修が欠かせません。
導入初期は、外部ベンダーの支援を受けながら操作に慣れ、段階的に自社内での運用へ移行する流れが理想です。また、取得したデータをただ記録するだけでなく、それをもとに判断・対応できる体制を整えることが重要です。データ分析の専門チームを設けたり、部門をまたいだ連携ルールを策定することで、異常検知から対応までをスムーズに行えるようになります。
さらに、日々の業務に忙殺されがちな現場では、予知保全の運用が後回しにならないよう、定期的なレビューや担当者の役割明確化も必要です。属人化を避け、継続的な取り組みとして根付かせるためには、現場全体での合意形成とマネジメント層の支援もポイントとなります。
セキュリティ対策も忘れずに行う
予知保全の実現には、IoTセンサーやクラウドなどのIT技術を活用しますが、それにともなって、サイバーセキュリティのリスクも無視できません。設備に直結するシステムが外部とつながることで、不正アクセスや情報漏えいの可能性が生まれます。特に、工場や施設の制御系ネットワークは長年外部接続を前提としない設計が多く、脆弱性を抱えていることも少なくありません。
具体的には、通信の暗号化やアクセス権限の管理、ファームウェアの定期更新、ログ監視などが基本的な対策となります。また、IoT機器はセキュリティ対策が不十分なまま導入されるケースも多いため、導入前に「どこまで安全対策が講じられているか」を確認することが重要です。
さらに、内部からの情報流出や設定ミスを防ぐため、関係者のセキュリティ教育も必要です。定期的な演習やルールの周知を通じて、リスクに対する意識を高める取り組みが求められます。予知保全の継続的な活用には、技術と安心を両立させるセキュリティ設計が不可欠です。
まとめ
予知保全は、センサーやクラウド、AIなどの技術を活用し、設備の異常を未然に察知する新しい保全スタイルです。従来の予防保全・事後保全とは異なり、データに基づいて壊れる前に対応できる点が大きな特長です。突発故障を減らして安定稼働を実現し、人手やコストのムダも最小限に抑えることが可能になります。
ただし、導入には適切な設備選定、運用体制の整備、セキュリティ対策なども不可欠です。段階的な導入と継続的な活用で、現場の資産を守る確かな仕組みとして根づかせていきましょう。